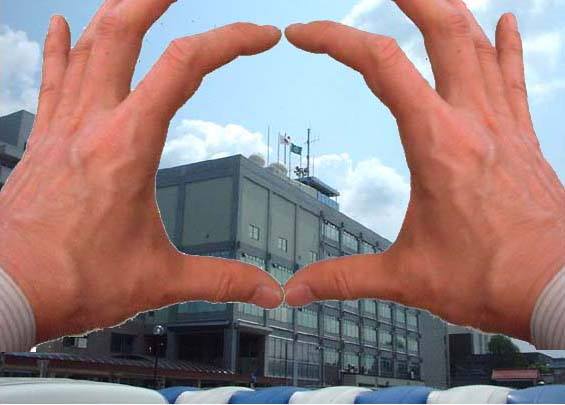当サイトの更新が遠のいている時は、FACEBOOKに投稿していることが多いので、そちらも合わせてご参照くださいませ。
The EMS SET with IPD-HELICOID includes all the functions that are required in the binoscope making.
All you have to do is to set a pair of the OTAs in parallel.
The focus change in adjusting the IPD is a minor issue, because when the gazers take turns the eyesight will be often re-adjusted regardless of the IPD.